本記事では、NIH(アメリカ国立衛生研究所)やFDA(アメリカ食品医薬品局)という、世界を代表する研究機関、規制当局が取り組む、動物実験に代わる安全性評価方法についての動向についてアウトプットします。
創薬や化粧品などの開発において、効果や安全性の試験は動物実験が主流でした。
しかし、動物愛護の観点はもちろんヒトと異なる結果が得られてしまい、動物実験では正確な評価ができないということで、NAMs(動物実験代替法)が注目され、開発が進められています。
FDAが2022年末に話題となったFDA近代化法2.0では医薬品開発における動物による試験の義務が廃止されるなど、着実に動物実験からの置き換えが進む方向に向かってきていると感じます。
そのFDA近代化法2.0から2年が経った2025年に、NIHとFDAから動物実験からヒトベースへの転換についてそれぞれ声明が発表されたので確認していきます。
再生医療・組織工学という人工的に臓器を作る研究についてまとめた研究まとめ。
「NIH」と「FDA」と「NAMs(動物実験代替法)」とは
NIHとは
NIHとは、「National Institutes of Health(アメリカ国立衛生研究所)」の略称です。
アメリカの国立がん研究所、国立心肺血液研究所、国立老化研究所などの研究所や図書館などで構成される政府機関です。
1887年に設立され、アメリカで最も古い医学研究所の拠点機関とのこと。(参考)
この機関の規模感として、2026年の予算は275億ドル(4兆円, 2025年7月)とのことで、これでも前年比40%減の金額だそうです。
日本全国の大学への研究費の総額が3.7兆円(2021年)なので、日本のすべての大学が束になってようやくアメリカの1つの機関に並ぶというイメージで、規模の大きさが伺えます。(参考)
NAMsとは
FDAとは、「Food and Drug Administration(アメリカ食品医薬品局)」の略称です。
米国内の医薬品や医療機器の安全性や有効性の確保をしたり、食品・医薬品などの信頼を維持することで、公衆衛生の向上を担う機関です。(参考)
日本で言うところの厚生労働省に近い機関とのこと。
NAMsとは
NAMsとは「New approach methodologies」の頭文字をとったものです。
定義は下記のものとされています。
単独、あるいは他の方法と組み合わせ、動物に保護的でヒトとの関連性の高いモデルを用い、化学物質の安全性評価を改善し、結果として動物の代替に貢献できるin vitro、in chemico、in silicoによるあらゆる方法
F Sewell et al. Toxicol Res. 2024.
これまで動物実験で行ってきた毒性評価の問題を解決するために、
迅速、安価、有益な新しいアプローチ方法の開発を目指したものです。
NIHの声明
NIHの今回の声明をまとめると下記の内容とのこと。(元記事)
- NIHは動物実験を削減する取り組みを導入していく。
- 後述するFDAの方向性とも合致している。
- 生物医学の研究で動物実験では、ヒトでの現象を再現することが難しい。
- 動物実験は完全になくすことはできないとした上で、動物代替技術を用いて、これまで動物実験でできなかったことを改善していく。
- NAMsとヒトベースの情報を用いて、健康や疾患の研究を改善することで、再現性や効率の良い結果が得られる。
- キーワードは「オルガノイド、臓器チップ、その他in vitroシステム」、「計算モデル(ヒトの複雑なシステム、疾患経路、薬の相互作用をシミュレーションする)」、「リアルワールドデータ(コミュニティや集団レベルのヒトの健康などの情報)」
- ヒトを基準にした研究アプローチを行うことで、イノベーションの加速、ヘルスケアの向上、より良い治療の提供ができるようになる。
- NIHがヒトに基づいた研究を推進するために、ORIVA(Office of Research Innovation, Validation, and Application)という機関を設立する予定。動物を使用しないアプローチの開発、検証、拡大を進めたり、資金提供と研修を拡大する取り組みを行うとのこと。資金提供の条件として、研究課題の適合性、Context of Use、応用可能性、ヒトへの関連性を満たしていることが必要とのこと。
- 動物実験への資金削減、ヒトを対象としたアプローチへの資金増加に向けた進捗状況を把握するために、研究支出の情報を毎年公表する。
FDAの声明
FDAの声明をまとめると、下記の内容とのこと。(元記事)
- FDAはモノクローナル抗体治療やその他治療薬の開発で、動物実験に変わる人に関連した方法を利用して効率化することに取り組む。
- キーワードは「AIベースの計算モデル」、「ヒト臓器モデル(NAMs)」、「リアルワールドヒトデータ」
- 薬の安全性改善や評価プロセスの促進、動物実験の削減、研究開発コストや薬の価格を低下させることを目的とする。
- IND申請(承認されていない医薬品を使用するための申請)に対して、NAMsデータを組み込むことがロードマップにも概説されている。
- 今回モノクローナル抗体の安全性評価で動物モデルからNAMsなどに置き換える利点は次の4つ
- 高度なコンピューターシミュレーションで動物実験の削減ができる
- ヒトベースの実験モデルによるヒトの応答をより直接的に理解できる
- より迅速な医薬品開発
- 薬の承認の早期化
- FDAはこのような取り組みを通して、レギュラトリーサイエンスにおけるグローバルリーダーとしての役割を進める。
- 国立衛生研究所などと連携し、動物実験代替法の検証に関するICCVAM(the Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods)という委員会を通じ、革新的な動物実験代替試験法の検証と採用の加速を目指す。
- 今後1年間で、モノクローナル抗体開発企業が動物実験を行わない試験を実施できるようなプログラムを開始する。
このような取り組みを行うことにより、ヒトベースの試験法を用いて実臨床の結果を正確に予測でき、安全性が高まることで、新しい治療法の開発が効率的になる。
更には動物福祉の向上につながることが期待されています。
この声明から思うこと
医薬品が低分子化合物から生物学的製剤への移行に伴い、開発費、開発期間が増加していることにより、いかに効率よく医薬品を作るかが求められるようになってきています。
そのような背景の中で、動物実験がヒトと異なる結果を示すことによる医薬品開発の失敗を回避することが一つの重要な取り組みになります。
これは、動物愛護の観点から動物実験をなくしていくことにもつながるため、ヒトにも動物にも恩恵の多い取り組みであることは間違いないでしょう。
そして、2022年末にFDA近代化法2.0によって動物試験の義務が撤廃されるということで、医薬品の開発状況はどのような影響を受け、どのように変わっていくのかについてとても気になっていました。
今回取り上げたNIHとFDAの声明は、どちらも動物実験代替法にさらに力を入れる内容になっており、FDA近代化法2.0での動きがより前向きに進んでいると考えられます。
どちらの声明でも、キーワードとして、「in vitro試験(オルガノイド、臓器チップなど)」、「計算科学(AI、シミュレーションなど)」、「リアルワールドデータ」が挙げられていました。
臓器チップの動向を見ると(過去記事)では、臓器チップで何がどこまでできるか明らかになってきており、次は社会にどのように受け入れられるかのフェーズになるとのことでした。
声明の内容としても、臓器チップなどの動物代替技術を実社会に導入していく視点であり、in vitroの評価系の社会実装がこれから更に着実に進んでいくと感じる内容でした。
FDA近代化法2.0と同様に、すぐに動物実験がなくなるわけではないけれど、今回の声明にあるように両機関とも研究資金の提供やプログラムの実施を通して、着実に動物実験が減っていく流れが加速していくと感じます。
組織工学の研究にそれなりに携わってきて、in vitroの試験系の実現は研究者だけでなく、企業、規制当局の全てが動いてようやく社会実装が達成できると言葉では理解していたものが、現実で見えてきたと実感するような内容でした。
まとめ
本記事では、NIH(アメリカ国立衛生研究所)やFDA(アメリカ食品医薬品局)という、世界を代表する研究機関、規制当局が取り組む、動物実験に代わる安全性評価方法についての動向についてのアウトプットでした。
生物学や医学、医薬品開発において当たり前のように実施されてきた動物実験について、これまでも動物実験の削減・廃止の動きはあった中で、更にそれが加速するような期待を抱く声明内容でした。
動物福祉の向上はもちろんのこと、NAMsなどの技術を用いることで、医薬品などのコスト削減、開発の早期化が達成されれば、ヒトにとっても恩恵は非常に大きいものなので、生命に取って幸福な取り組みであると思います。
これからも、NAMsなどの動物実験代替法の動きについて注目をしていきます。

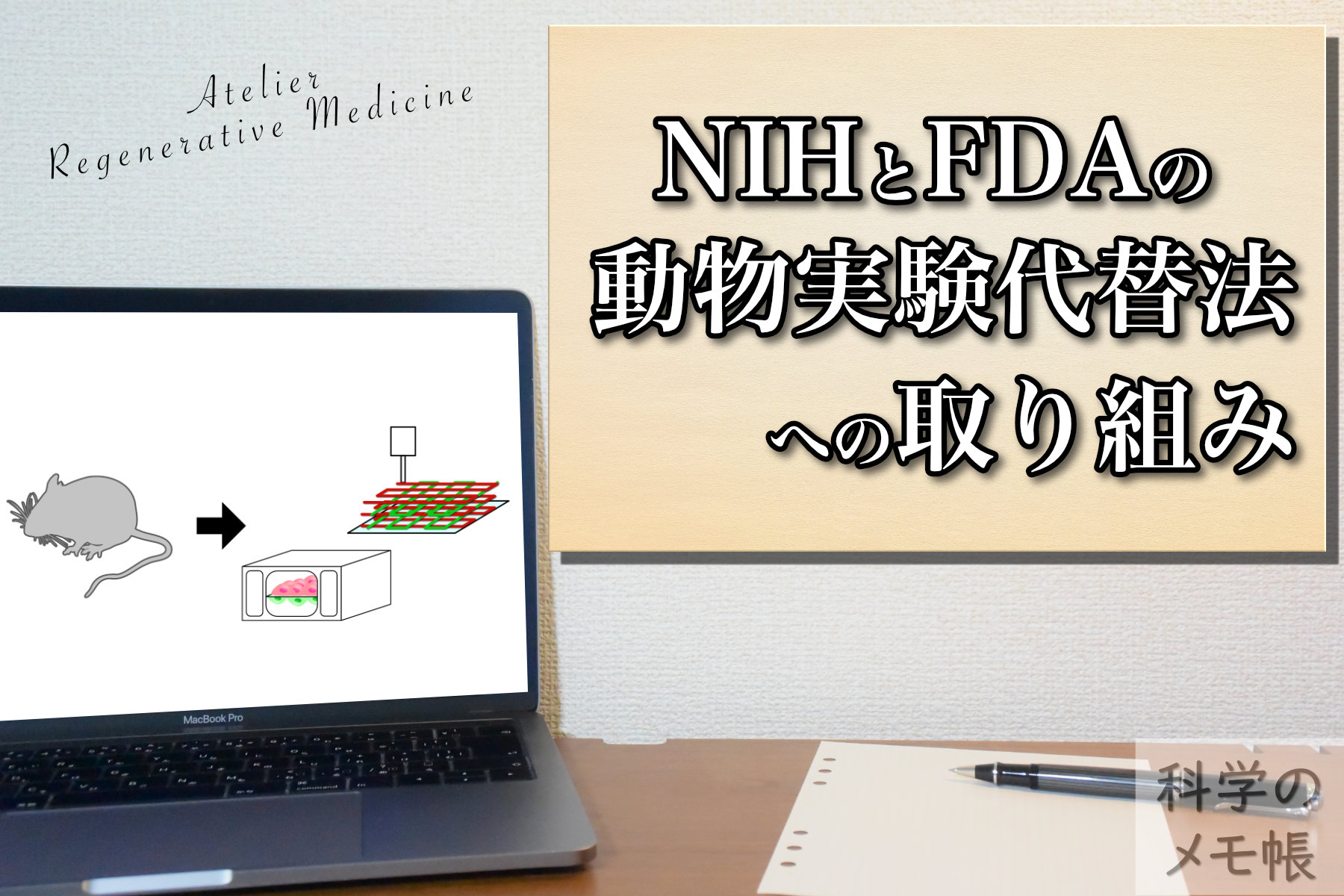


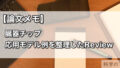
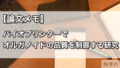
コメント