再生医療や創薬の発展のために、臓器の構造や機能を再現できるオルガノイドを作製する技術が注目されています。
現在のオルガノイド作製技術は、それなりに狙った臓器の特徴を持つ3次元組織を構築することができるようになってきています。一方で、スケールアップ、クオリティコントロール、スループット性の問題を抱えていると言われています。
この問題は人が手作業によりオルガノイド培養を行っていることが一因と言われています。
今回ピックアップする論文はそのオルガノイド培養の分野で、腎臓のオルガノイドの作製方法に焦点を当てたものです。
オルガノイド構築における品質やスループット性の問題を解決するために、プリンターの技術を使ってヒトの手を介さずに、再現性の高い腎臓オルガノイドを効率よく作製する方法の開発に取り組んだ研究です。
タイトル:Cellular extrusion bioprinting improves kidney organoid reproducibility and conformation.
著者:Kynan T. Lawlor et al.
雑誌:Nature Materials
リンク:PubMed
再生医療・組織工学という人工的に臓器を作る研究のまとめ。
研究の背景とか課題とか
再生医療・創薬開発の研究において、ごく当たり前に実施されているin vitroでの細胞アッセイ。
この時、プラスチック製の培養容器で、細胞を2次元平面で培養した状態で使うことがメジャーですが、細胞は体の中と大きく異なる環境で培養されることになります。
これにより、細胞が本来持つ臓器の機能が消失するなどの原因により、因子や薬の正確な応答性が検出できないなどの問題があります。
その解決策として、分化を制御しながら幹細胞培養することで、臓器のような構造を持つ細胞の凝集体「オルガノイド」を構築する技術が注目されています。
このオルガノイドは、従来の平面状態で培養した細胞よりも生体に近い構造・機能を持っており、再生医療・創薬での強力なツールとして期待されています。
一方で実用化するために解決すべき課題も多くあり、そのうちの一つが、オルガノイドを培養するプロトコルが複雑なことによる、実験の再現性、スループット性が低いというもの。
この背景に対し、この研究ではバイオプリンターを利用して、オルガノイド作製時の課題である品質コントロールとスケールアップに取り組んだとのこと。
プリンティング技術は材料の空間配置制御を得意としており、この機能を使って手作業よりも再現よく高速に細胞を配置できるところに注目したようです。
これにより、手作業と同程度の機能を持ったオルガノイドの作製の再現性向上や自動化が達成できるとのことです。
論文の概要
実験の大まかな概要は下記の通り。
- 3Dプリンターとして、押出方式のものを使用。
使用した3Dプリンターの機種はNovoGen MMX extrusion-based 3D cellular bioprinter
(バイオプリンティングについてのまとめ記事) - 単離したiPS細胞をプリンターを用いてカルチャーインサートにドット状やライン状に印刷し、分化させることで腎臓オルガノイドを作製。
- 手作業で作製したオルガノイドと構造、機能の比較を実施。プリンターは人の手の代わりにオルガノイドをつくることができるのか?どこまでコントロールできるのかを検証。
結果は下記の通り。
- プリンターを使ってオルガノイド作製を自動化することで、1オルガノイド/3秒で作製できる
- オルガノイドのサイズ(直径)が均一に揃っている
- 手作業に比べて、1つのオルガノイドを作製するための細胞数が1/50倍(4×10^3 cells)に削減
- 1ウェルの中に複数個のオルガノイドを並べて作製することができる。
- プリンターでオルガノイドの形状を制御することで(ドット状、ライン状)、ネフロンの形成度合いを制御できる
注目したこと
再生医療や創薬におけるオルガノイドの利活用で、再現性が低いことや品質のばらつきなどの課題があるということは聞いていました。
その課題に対して、バイオプリンティングの技術で細胞播種のステップを改善することで、オルガノイド作製の品質コントロールができるところに特に興味を持ちました。
これまでバイオプリンターは立体造形をするための技術という認識が強かったので、このような品質コントロールのために使う使い方は驚きでした。
確かに、バイオプリンティングは一定量のインク材料を適量、精密に配置する事ができる技術であるため、得意分野であることはその通りで、コロンブスの卵を見た気分です。
また、オルガノイドの初期の形状をドット状かライン状かにするだけの簡単な構造制御で、分化後のネフロンの形成量が変わる事も気になるところです。
この論文の結果では、ネフロン量を増加させるためにはライン状が良いとのことでしたが、解析等の都合を考慮するならドット状の方がスループット的には嬉しい所だったでしょうか。
ドット状でもネフロン量を増やすことができる培養方法などがここから開発されていくと面白いと思いました。
まとめ
以上、腎臓オルガノイドの作製の課題である再現性やスループット性をバイオプリンティング技術で解決する試みの研究でした。
個人的には機械を使う意義を改めて考えさせられた論文でした。
再生医療・創薬の低コスト化をするためには様々な解決すべき課題がありますが、この論文はその課題に対して機械を使うことで解決できる部分について示したものだと思います。
優れた技術者が職人の手技で1点もののオルガノイドを作っても、実用化には程遠いですからね。
というだけでなく、細胞培養の世界では、実験者による細胞の扱い方の違いでも再現性に影響が出るということも言われています。
機械を使って、人の手が入らないようにする事は、再生医療・創薬の低コスト化のみならず、実験をどこでも誰でも統一できる可能性を秘めているという事でもあると思います。
バイオプリンティングの技術は立体造形だけでなく、品質コントロールのような使い方もこれから注目して見ていきたいと思います。

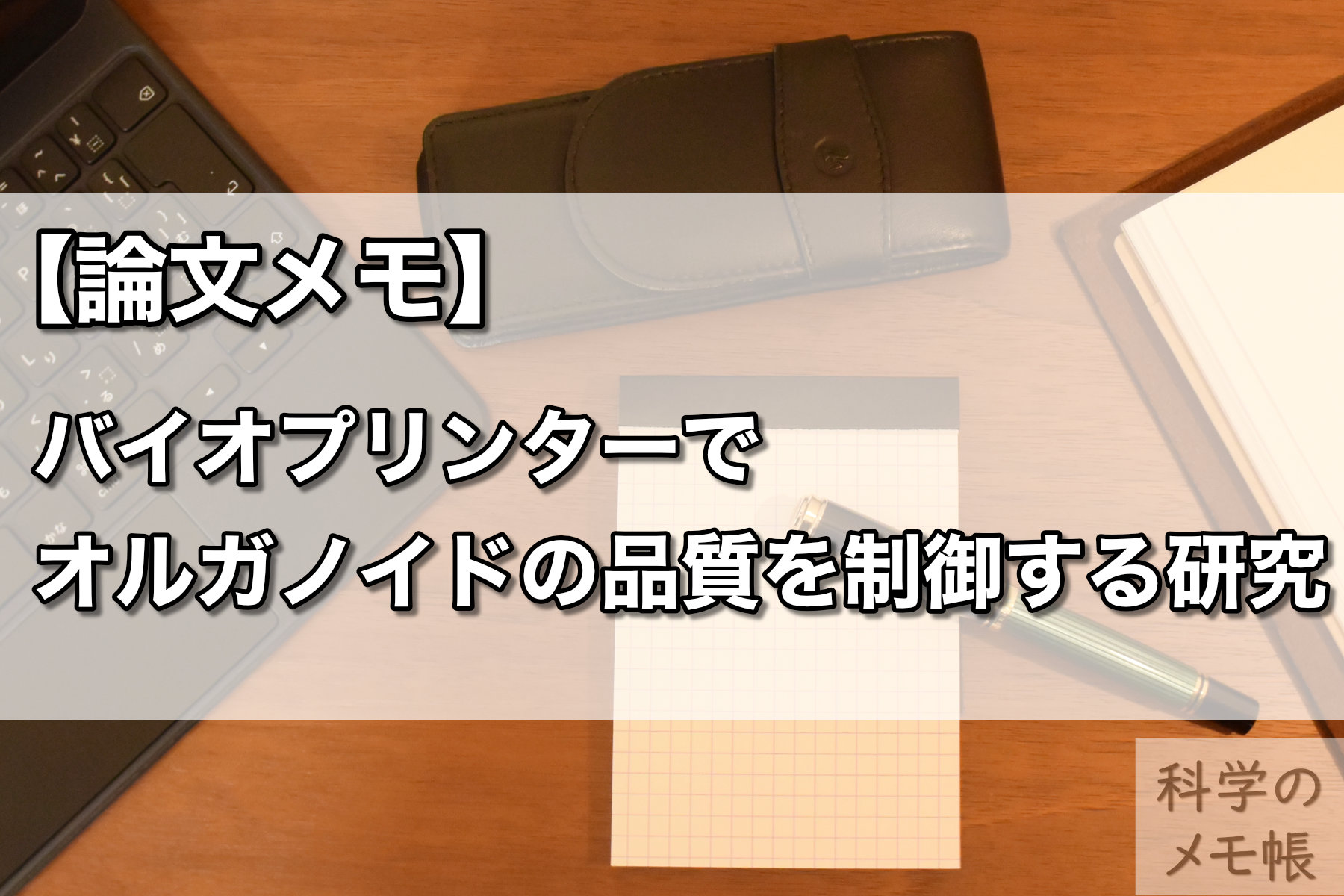


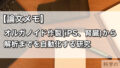
コメント