医薬品が高度化していることで、開発コストが年々増加しており、その開発期間は9〜17年、開発費は数百億〜数千億円と言われています。(過去記事)
この解決策として、動物実験よりも正確にヒトへの薬効や毒性が評価できると考えられているin vitroの試験方法の開発が進められてきています。(過去記事)
この中で注目を浴びているin vitroの細胞培養方法がオルガノイドで、従来の培養形態より臓器の構造や機能をより再現していると言われています。
また、数十万以上ある薬の候補の中から有効なものを探し出すための効率的な試験方法として、大量のサンプルで大量の試験を自動で実施できるハイスループットスクリーニング(HTS)という手法があります。
人の手では再現性よく多量のサンプルを処理することは限界があるので、ロボットなどを駆使した自動化が鍵になってきます。
そんな医薬品開発などの効率化の背景において、iPS細胞からオルガノイドへ分化→評価→解析を自動化しHTSのシステムを構築することに取り組んだ研究について、当時(2018年)それなりに先駆的だったであろう論文を読んだのでそのアウトプットです。
再生医療・組織工学という人工的に臓器を作る研究のまとめ。
論文情報
著者:Stefan M Czerniecki et al.
雑誌:Cell Stem Cell
研究の背景とか課題とか
まずはこの研究が取り組まれた背景について。
創薬において、数十万以上の候補から薬となるものを絞り込むためのハイスループットスクリーニング(HTS)という、多量のサンプルを用いて多量の薬の候補の効果を調べる手法が用いられています。
このとき、細胞を用いた評価では、従来の2D培養のような単純な培養方法では薬の作用を正確に測定することができないことが問題視されています。
そこで、より生体に近い構造や機能を持つオルガノイドを用いることで、より正確な評価ができるということで、オルガノイド+HTSの評価方法が開発されてきているようです。
しかし、オルガノイドを用いた評価の課題として
- オルガノイド作製の煩雑なプロトコル
- 長い培養期間
- 解析のための染色などの処理
が、自動化や小スケール化の障壁となっているようです。
また、この当時報告されていたオルガノイドを用いた自動化の系については、オルガノイドは既にある程度分化している体性幹細胞を用いたものがほとんどで、iPS細胞からオルガノイドに分化して解析するまでの工程を自動化した報告はなかったようです。
そこで、この研究はiPS細胞を用いたオルガノイドのHTSの自動化を目的として、iPS細胞からオルガノイド(腎臓)へ分化させ、解析するまでの一連の工程を小型化、自動化することで、完全自動化オルガノイドHTSを行う仕組みの開発に取り組まれていました。
論文の概要
大まかな実験内容として、
- 自動リキッドハンドリングロボを用いて播種→分化→固定化→表現型解析の自動化
- HTSオルガノイドの定量評価、分化状態、生成物の解析を実施
- 分化で用いるCHIRの添加量の最適濃度が不明であったため、定義する
- オルガノイドのマーカー解析・シングルセル解析によって、オルガノイドに含まれる細胞種の解析
- オルガノイド中の血管の発達を解析
- オルガノイドを用いて毒性評価、疾患の表現型についてHTSの自動化の実施
その結果としては、
- 96, 384 wellプレートでオルガノイド作製の自動化ができた
- 分化にかかる期間は3週間で、腎臓と類似した細胞が含まれ、ネフロン構造を持っている
- 血管の構造としては、VEGFを添加しても構造は未成熟
- 使用するiPS細胞のサブクローンが異なると最適の分化誘導試薬の濃度が異なり、分化の安定性はサブクローンごとに異なる
- オルガノイドを用いたHTSの細胞毒性評価や、疾患の表現型について、試薬濃度依存的な細胞毒性(アポトーシス)を確認。腎臓疾患のエンドポイントとされている嚢胞形成を確認。
- これまで知られていなかった疾患に関する因子の発見ができた
注目したこと
この論文を読んで、個人的にポイントだと思った部分が、オルガノイドの分化で煩雑なプロトコルを避け、1ステップでiPS細胞から腎臓オルガノイドへ分化ができるプロトコルを採用したこと。
この研究ではシンプルなプロトコルを割りきって採用しており、引き算の美学を感じる部分でした。
自分だったら、代表的で煩雑なプロトコルを、あの手この手でロボの動きなどを改造して対応させるだろうなと思いました。
シンプルなプロトコルにしたためにオルガノイドの成熟度は低いものになったようですが、目的の評価ができることとそれに必要なオルガノイドの分化レベルが一致していれば良いので、使用用途によっては完璧なものを目指す必要ないのかなと。
今回の成熟度では足りず、より成熟したオルガノイドが必要な場合、すでに構築しているこのシステムでプロトコルを最適化して行けば良いので、まずはそのための基盤を作ったというところが重要なところだと思いました。
また、同じiPS細胞の株でも、使用するサブクローンが異なると最適な分化条件(CHIR濃度)や、分化の安定性が異なるところも非常に興味深かったです。
分化の安定性をZ’-factorという指標で表現しており、あるサブクローンは非常に安定したオルガノイド分化ができておりHTSに適合するが、別のサブクローンは不安定でHTSに適さないと判断されるものもあったとのこと。
細胞を使った実験の再現性の担保が難しいと言われていることがよく分かる実験結果でした。
HTSに適合する細胞かどうかを見極めることも重要で、これを自動化して効率化できるのがこの研究成果の重要なところの一つだと感じました。
効率化、コスト削減において自動化は欠かせないもので、ますますロボなどを導入した研究の自動化への取り組みが増えてきたことで意識しなくても耳にすることが増えてきたように感じます。
まとめ
以上、iPS細胞をオルガノイドへ分化→評価→解析を自動化する研究についての論文でした。
自動化ということで、オルガノイドの分化方法の目新しさはなく、再現性といった細かいところのデータ等やや地味ではあるものの、実用化のためには着実な一歩を進めるための非常に重要な研究だと思いました。
ヒトが実験すると作業者間での再現性のばらつきなんかも気になるし、もっとたくさんの仮説を考えて実験をたくさんしたいことを叶えたいと思うので、日頃の実験も自動化できたらいいなぁと。

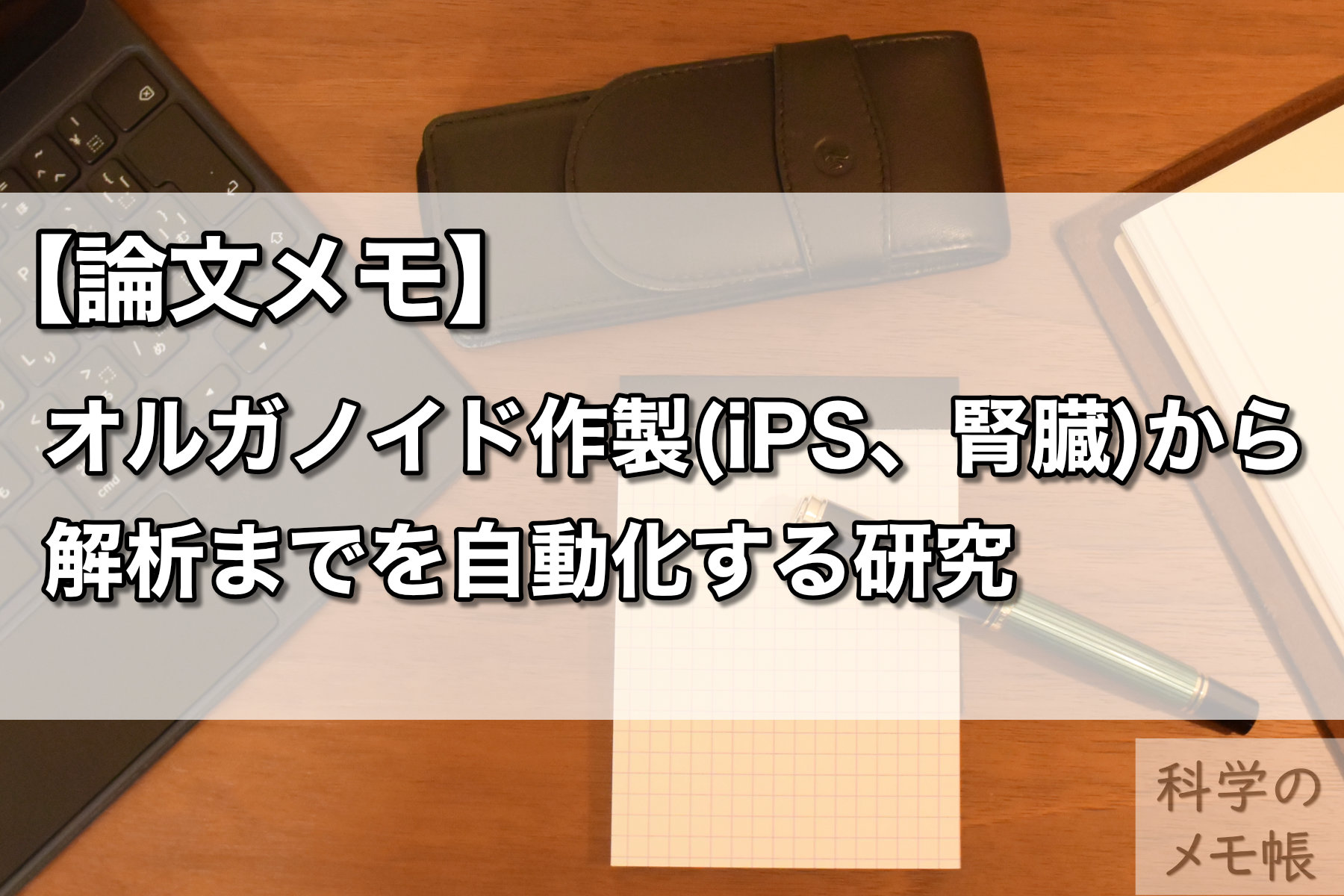

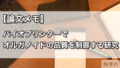
コメント