薬の開発のコストが年々増加していることが問題視されています。
開発コストが上がることにより、製薬企業の開発リスクが上がるだけでなく、我々の医療費にも影響し、安全で健康な生活の維持に関わる問題です。
コストが増加する要因としては色々ある中で、薬の有効成分を探索する評価に使用している細胞培養技術や動物実験の限界が一つの要因とされています。
近年FDAなどで、医薬品の承認において、非臨床試験での動物実験の義務を撤廃するという発表がありました。
これにより、in vitroの評価系としてOrgan-on-a-chip(臓器チップ)の技術の注目が大きくなっています。
この臓器チップ技術は、小さなチップ上で人の臓器の一部分の構造や機能を再現することで、薬の効果を理解することを目的としています。
これにより、従来の培養細胞や実験よりも正確に薬の効果や毒性を判定し、薬の開発の失敗を無くすことで、開発コストを下げることが期待されています。
今回ピックアップする論文は、この臓器チップに関するReview論文で「Advances in organ-on-a-chip engineering」で2018年にNature Reviews Materials (R)に掲載されたものです。
執筆時は2025年5月と7年前の論文ですが、そこから今どうなっているのか確認すると発展の様子が掴めそうです。
再生医療・組織工学という人工的に臓器を作る研究のまとめ
臓器チップの背景とか課題とか
臓器チップの開発は1991年のAnder Kleberらの研究がスタートと言われています。(R)
1990年後半にはマイクロフルイディクスという流体制御技術のバイオでの活用が盛んになり、2004年にはシリコンチップ上での肺や肝臓のモデル構築が行われました。(R) (R)
そこから血管、脳、腸、腎臓など様々な臓器機能を再現したモデルが構築され、2010年には肺の血管と肺胞の界面の機能を模倣した肺の臓器チップが開発されています。(R)
この研究は臓器チップの中でもかなり大きな影響を与えたもので、被引用件数は何と4600件(2025年5月)もあります。
そんな臓器チップの研究の発達とともに、臓器チップの役割として、創薬研究の開発に大きく貢献できる可能性があることも見えてきました。
創薬では薬の有効性だけでなく、安全性も非常に重要視されています。
薬の開発では、培養細胞による評価や動物実験による薬の有効性と安全性を確認し(非臨床試験)、ヒトでの試験を実施(臨床試験)する流れとなっています。
しかしこの方法、非臨床試験では有効で安全とされたものが、臨床試験でヒトに投与すると有効性がなかったり、最悪だと毒性を示すこともあります。
お金と時間をかけ、薬の候補物質を絞り込んできても培養細胞や動物実験による評価方法ではヒトでの反応を正確に再現できず、結果、最終ステップで開発が頓挫することが問題となっています。
(薬が開発されるまでに、約14年程度、数百億〜数千億円かかるうち、臨床試験実施まで大体8年程度も費やすようです。)(参考)
その結果、2018年時点で新しい薬の承認は20年間で減少しているとのことです。
この問題の原因の一つが、培養細胞や動物実験の評価結果の予測精度の低さということです。
よりヒトに近い構造、機能を再現できる臓器チップなら、有効性も毒性も正しく評価できるのではということで、創薬の世界で注目されているわけですね。
このように、薬の開発に臓器チップを用いた開発効率改善の目的のために、2018年の時点で、製薬企業、規制当局、国家防衛機関が臓器チップ技術に注目していたようです。
2018年までの7年間で臓器チップに関連する企業が28社もでき、製薬企業と連携しながら臓器チップの実用化に取り組まれています。
このような臓器チップ技術の分野の動向に対して、このReviewでは次の項目について、整理・解説しています。
- 臓器チップの3つに分類
- バリア機能組織
- 実質組織
- 多臓器連関
- 臓器チップの開発における重要な要素
- 細胞ソース
- 機能的特徴
- 疾患モデル
- 開発をより発展させるための課題
- 材料
- 細胞
- 多重化
- センシング
- スケーラビリティ
- バリデーション(検証)
Reviewで注目した内容
臓器チップの分類
まずは、血管と上皮系の器官(血管網、肺、腸)組織におけるバリア機能について。
微小な流路構造であるメリットを最大に活かした使い方だと思う。
メンブレンやハイドロゲルを用いた血管を通る流体からの物質通過という動的な現象の再現は臓器チップならではでしょう。
ハイスループット化のためにMimetas社のウェルプレートフォーマットの流体デバイスがピックアップされていましたが、2025年現在ではその存在感も大きく、実際に非臨床試験としても用いられた報告もあるほどです。
次に、実質細胞の組織(肝臓、心臓、骨格筋、がんなど)について。
このReviewでは特に薬の毒性が問題になっている、心臓と肝臓の組織についてまとめられていました。
血管-上皮界面の臓器チップは扉のようなもので、実質細胞組織は家のようなものとの位置付けで、心臓や肝臓の臓器チップでは、いかに臓器の3次元的な構造や機能を再現するかという技術が紹介されていました。
デバイスの構造の工夫はもちろん、心臓であれば電気や機械による刺激を与える培養方法で成熟化を促したり、肝臓であれば3Dプリンターやオルガノイド培養技術を用いて特徴的な構造を再現したりと様々な視点からの取り組みがまとめられていました。
また肝臓の臓器チップも商用展開している企業もあるようで、最近の報告では創薬開発に肝臓チップを用いる経済的なメリットを示すものもあります。(R)(Emulate社)
そして、多臓器の連関について。
血管などのバリアを通過し、吸収された薬が臓器にどのように作用し、それがさらに他の臓器に移動して作用するかという臓器同士の繋がりを調べるための、臓器チップの究極体。
特に、体全体での吸収、分布、代謝、排泄(ADME)という薬物動態を調べたり、免疫などの臓器間を循環するような細胞の働きを調べたりするための重要なツールとして期待されています。
実際に13種類の臓器を連結したようなBody-on-a-chipのコンセプトを実証した報告もあるようです。(R)
臓器チップの課題
課題の項目として下記の項目が挙げられており、これはそのまま臓器チップの実用化までの要素でもあると思いました。
- 素材
- 細胞
- 流体制御
- データ取得
- スケールアップ
- 標準化
【素材】
材料は臓器チップの開発当初から用いられているPDMSで良いのでは?とも思うところですが、薬剤の吸着性が課題です。
ただし、必ず改善が必要かと言われればそういうわけでもなく、評価したい薬剤の性質(吸着しやすいかどうか)次第とのこと。
【細胞】
細胞はよく言われている成熟化が注目すべき点です。
特に幹細胞から分化した細胞は未成熟で機能が発達しておらず、ヒトでは新生児ぐらいの細胞に近い細胞と言われることが多いです。
成人に効果がある薬の開発においては、より成熟した細胞を作る技術が必要で、2025年現在でも成熟化に関する研究が活発に取り組まれています。
また、細胞のメーカーなども、機能が成熟した細胞を製品の競合優位性として販売しており、そのような成熟した細胞の使用例を見ると、いかに良い細胞を使うかが評価系の土台として重要そうです。
【流体制御】
このReviewでは、流体制御についてポンプ有りとポンプなしの比較がされていました。
ポンプを使って精密に流体を制御したほうが、体の中の血流を忠実に再現できる可能性が高いです。
しかし、気泡やコンタミに気を使いながら組み立てる技術や、コスト、一度に評価できる数の限界が実用化のところでネックになるとのことでした。
これに対し、重力駆動による流れの方では、すこしラフな流れの制御になりそうですが、誰でも使える、スケールアップしやすい観点から、現場では導入しやすい点が実用化の観点からも重要とのことですね。
【データ取得】
データ取得では、臓器チップ内での動的な薬の分布や細胞などの動きを再現できることから、リアルタイムなデータ取得は重要なポイントとされています。
広く使われている顕微鏡を用いた方法では、細胞一つ一つの動きなどを詳しく非侵襲で追えますが、同時に観察できるポイントが少ないところが実用化におけるボトルネックとなる部分です。
そこで、センサーやプローブを用いることで、電気的あるいは光学的なセンシング方法が有効だろうとのこと。
マイクロレベルの小さな構造の中にセンサーを搭載し、細胞を上手く乗せ、再現良い測定をしようと思うと、実験レベルの少サンプルでは扱えても、商業レベルで扱う数が増えるとなかなかハードルは高そうですが、実現できれば大きく発展しそうです。
【スケールアップ】
スケールアップも臓器チップ開発で重要視されています。
実験室レベルでできていたことが、商業用レベルのスケールに拡大すると再現できなくなるのはよく聞く話ですね。
特にOoCの作成工程は細胞も使用するため、デバイスの製造品質に加えて、細胞の品質やロット間の機能差も影響するためかなり複雑になります。
さらに、センサーも組み込もうとすると前項で触れたように、さらに複雑になります。
これを大量生産し再現性を確保しようとするとかなりのハードルになることは想像に難くないですね。
この課題に対しては、デバイスの複雑性と製造性はトレードオフのため、妥協点を見つける必要があるとのことでした。
【標準化】
標準化はOoCの実用化に向けて一番大事なところです。
動物実験や既存のin vitroの代替法となるためには、それよりも良い(=生体に近い)機能があることを示す必要があります。
生体の何を再現できていて、どこがまだできていないのか。その状態でどこまでのことを評価できるのかを、きちんと証明しながら受け入れられていく必要があります。
FDAなどの規制当局や開発者と製薬企業が協力しながら実用化のための標準化がとりくまれており、2025年現在はこの点が非常に注力されていると感じます。(参考)
応用について思うこと
臓器チップは培養皿上でただ細胞を培養するよりも複雑で高い機能を持つことができる所が大きな一つの魅力です。
しかし、複雑になるほど取り扱いが難しくなったり、再現性が下がったりと実用化のハードルが上がるという難しさもあります。
Reviewの中でも、評価に必要な機能を見極めて、チップをデザインすることが必要とのことでした。
人体を完全に模倣するような理想の臓器チップを求めて、複雑な構造になりすぎた結果、限られた人しか使えないものになるより、現実的な妥協点で誰でも使える臓器チップにすることが広く受け入れられるために重要な考え方ですね。
完全な体の中を再現することは現実的ではない状況の中では、評価したい項目に合わせた要素を、いかにシンプルに実装するかが鍵ということでしょう。
とは言うものの、何が必要な要素なのかを判断することがまた難しいところだと思います。
何を評価したら良いのかわかっているならば、薬の予期せぬ反応が生じることがなくなるわけで、わからないからこそ実装しながら判断する必要があるとも考えられます。
まさに卵が先か、鶏が先かに通づるものがあります。
そんな答えのない中、研究者たちは模索しながら臓器チップの開発を進めているのでしょう。
まとめ
今回紹介したレビュー論文は、Organ-on-a-chipの分類や課題の整理がされており、OoCの発展をさらに高めるための開発要素を明確にしてくれていると感じるものでした。
特に、Organ-on-a-chipの基板材料としても、学会の企業ブースなんかを見て回ると、各社PDMSに変わる素材のものを開発していたり、センサー組み込み型のものも開発されていたりしている。
このReviewで取り上げられていた臓器チップのメーカーの活躍も目にしています。
課題として挙げられていたものが実用化されてきていて、このレビューの考察通りの開発となっているため、このReviewは、かなり要点をついていたものだと感じました。

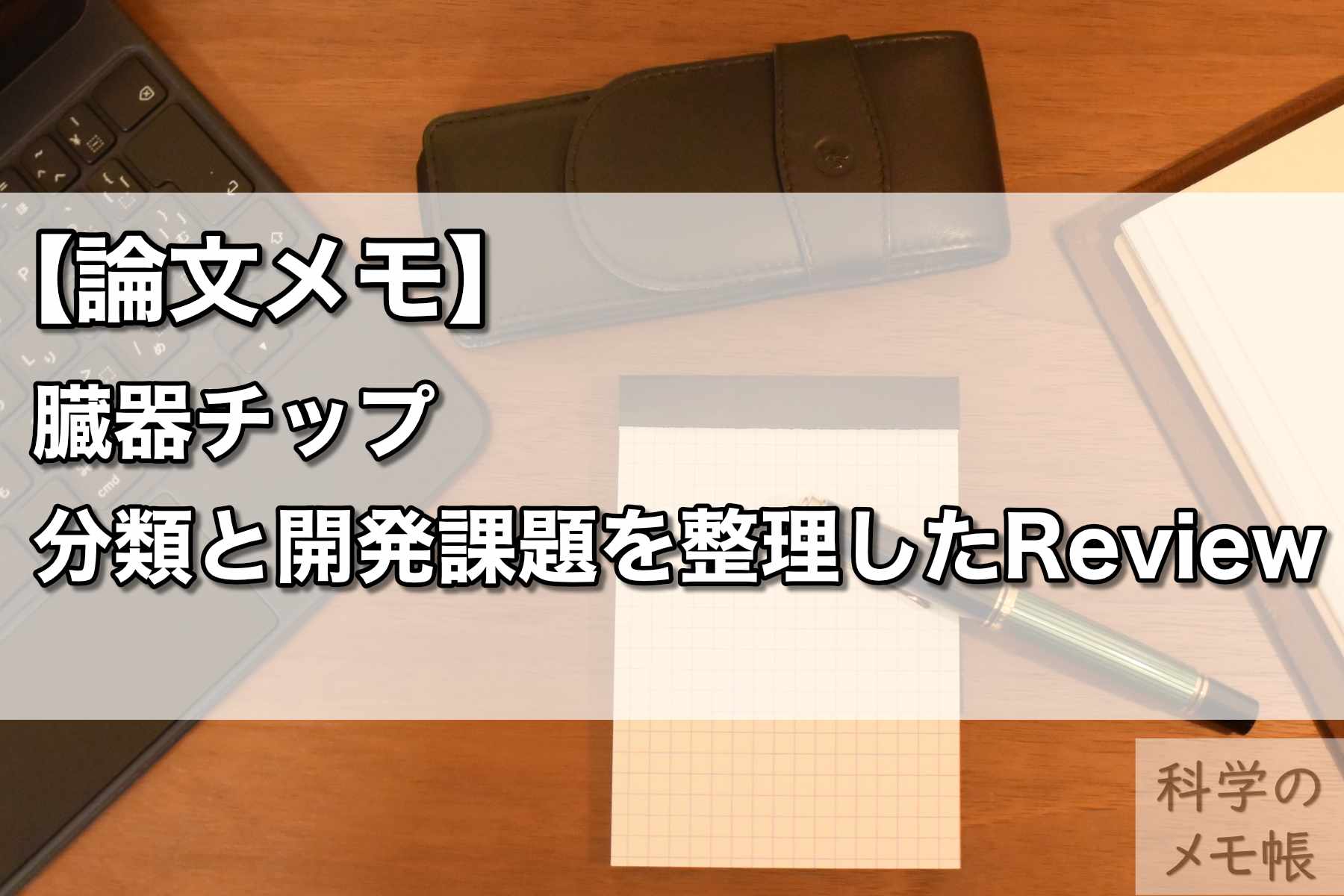


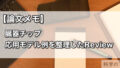
コメント