本記事では「細胞中での相分離による抗がん剤局在が効果に影響する」という面白い論文を読んだのでアウトプットしていきます。
最近話題の「細胞内での相分離」についての研究が、これまでうまく説明できなかった生命の機能を説明できそうとのことで注目されているようです。
過去記事(「相分離生物学」を読んだ感想と学んだことのメモ)で勉強した「相分離生物学」という本では、主に細胞が本来持つ生命現象について相分離の観点から解説されていました。
このとき疑問に思ったのが、薬剤などの細胞外から取り込まれた人工的なものについては相分離とはどの様に関わるのか?というところです。
上記の疑問に対して、Isaac A Klein et alがScienceで「抗がん剤と細胞内での相分離」について研究した結果が報告されていました。
結果としては、薬剤も細胞内での相分離による影響を受けることで、効率よく作用したり、薬剤耐性を持つ可能性があることがわかってきたとのことです。
非常に面白い論文で、細胞と材料をいじって機能を持つものを作る研究者として応用して色々できる可能性があるのではと感じました。
細胞内での相分離とは
細胞の中では、「液-液相分離」という現象によって、細胞の中のものが区画化されていることがわかってきているそうです。
詳細については過去記事で触れています。
ざっくりと細胞内での相分離にまとめると、細胞内のタンパク質やRNAが凝縮することで細胞内で液滴を形成するようです。
液の中に液滴ができる不思議な状態ですが、この液滴の機能としては
- 濃縮
- 安定化
- 連続反応
などの、生命の機能維持のために重要な機能を実行する場となっているのではないかとのことが研究でわかってきているようです。
相分離によって細胞内で薬剤も局在することがわかった
抗がん剤の液滴の局在化と作用の効率化
これまでの細胞に取り込まれた薬が作用するイメージとしては、細胞内に取り込まれて、均一に分散した状態でターゲットとぶつかって作用するというものでした。
ところが、とある抗がん剤は細胞内に取り込まれたあと、核内にある相分離した液滴の中に局在化されることで作用を発揮しているのではないか?という研究結果が報告されていました。
研究結果によると、遺伝子活性化タンパク質であるMED1が形成した液滴の中に、シスプラチンという抗がん剤が局在化することが確認されたとのことです。
そして、このシスプラチンが局在化した内部で、シスプラチンの作用で変性したDNAが多く確認されたそうです。
さらに、
- シスプラチンが局在しないようなMED1以外のタンパク質が構成した液滴では、上記の様な変性したDNAは局在していなかったとのこと。
- MED1を減少させることで変性したDNAの量も減少したとのこと。
といった結果からも、MED1に局在したことで、シスプラチンが効率よく作用しているということが考えられるとのことです。
まさに相分離で解説されていた「細胞内での反応の場」として液滴が機能している結果となっていて面白いと感じました。
「相分離生物学」では細胞の内部での本来持っている反応について解説されていましたが、この研究結果のように、細胞外から取り込んだ薬剤の反応も、相分離が関与しているというのは興味深いところですね。
液滴への局在化と抗がん剤の薬物耐性
さらなる応用として「タモキシフェン」という抗がん剤を用いた、薬剤耐性についての結果も興味深かったです。
タモキシフェンもシスプラチンと同様にMED1の液滴に局在化する薬剤だそうです。
タモキシフェンに耐性のあるがん細胞を調べてみるとMED1が通常の細胞よりもかなり多く産生していることがわかり、
その結果、各液滴内のタモキシフェンの濃度が減少するため、反応の場としての作用が弱まってしまったことが考えられるそうです。
がん細胞と一言に言っても、ある薬剤が効くものもあれば、効かないものもあり、受容体の発現が少ないからとかタンパクが変性していて薬剤の結合部位が変化しているからかとか思っていました。
ところが、反応する場での濃度が低くなっているという環境的な要因ということを相分離という観点で説明ができるのがやはりスッキリするなと思いました。
特異的に薬剤を局在化することの応用を考えてみる
この論文を読んで、何かしら応用できないかと色々考えてみました。
私の注目点は、液滴を構成する材料特異的に、特定の薬剤が局在するところです。
マイクロ流路を用いて小さな液滴やゲルを作製する研究があります。(参考:PubMed)
これを使って、細胞と評価したい薬剤を特異的に局在化させる材料を混ぜてゲル(液滴)を作ります。
この時に、薬剤特異的なゲル材の濃度を変えることで、ある一定の濃度の薬剤を添加した時に、薬剤濃度の調整をすることなく、ゲル中の材料濃度に応じて薬剤が勝手に濃度が割り振られるので、スループットの高い評価系が作れたら便利だなと思いました。
(もちろんマイクロ流路自体で濃度勾配を作る研究(参考:PubMed)もありますが、実際にマイクロ流路を使ってみると安定するまでがかなり大変だったり、繊細だったりでなかなか実用的にするの難しいかなと思っていますが、そこらへんどうなんでしょうか?)
今回取り上げた論文でも、薬剤が液滴に局在化する原理として、タンパク質中の芳香環が関与しているとのことで、薬剤の性質に合わせて材料を作ってやると意外とすんなり制御できるのではないかなと思います。
細胞内に比べてスケールはかなり大きくなりますが、できたら他にも応用できそうで妄想が膨らみますね。
まとめ
以上、「細胞中での相分離による抗がん剤局在が効果に影響する」についてのアウトプットでした。
「相分離生物学」という教科書を読んだ時もそうでしたが、これまで「なんでこうなるの?」という疑問にたいして、ある視点からみるととても綺麗に説明できるというのはかなり気持ち良いなと思います。
綺麗に説明できるだけでは本当にそうなのかという証明にはならないので、これからも検証が必要なのかもしれないけれど、一歩前進していることは間違いないので、新しい視点からのアプローチって大事だなと感じます。
相分離生物学という分野を少しかじって論文とかも少し目を通してみると、応用できそうなことがいっぱいあって楽しいですね。
基礎研究によってこれまでわからなかったことを理解して、その知見をどの様な形にして、恩恵を受けていくかを追求するのがやはり工学系の分野として面白いところだなと思います。

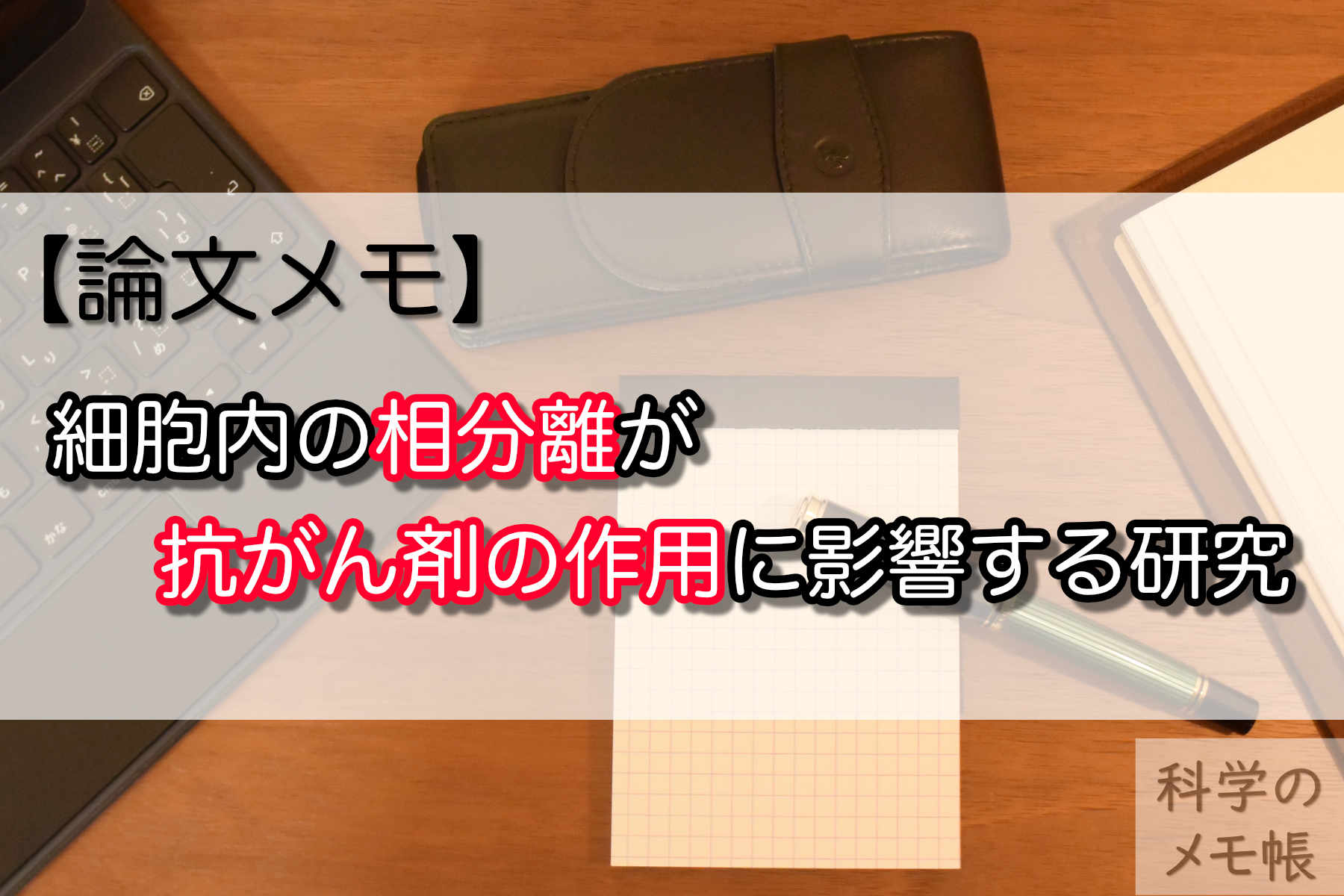
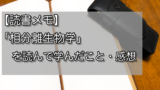
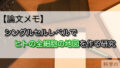

コメント