本記事では、「相分離生物学」を読んで学んだことをアウトプットします。
細胞の中ではある特定条件下で、膜のない液滴(ドロップレット)が形成されて、この液滴が実は生命の機能を維持するために非常に重要な働きをしているのではないか?ということが近年注目を浴びているとのこと。そしてこの液滴について探求するのが「相分離生物学」という学問領域とのことです。
「相分離生物学」が発行されたのが2019年でかなり話題になり、私がこの本を読み本記事を執筆しているのが2021年と非常に今更かつ、内容についてあれこれ噛み砕くのも野暮というものなので、気になる人はぜひ自分で読んでみてほしいです。(かなりわかりやすく解説されています。)
ということで本記事では、「相分離生物学」を読んで、
- 面白かったところ
- 疑問が残っているところ
といった、読んでみた私の感想や考えたことについてアウトプットしていきます。
相分離生物学を読んでみての全体的な感想
相分離生物学への誤解
本書籍のテーマである「液-液相分離」について、多少聞いたことがあり、細胞内のサイトゾルの中で、相分離が起こることが不思議だなというものだと思っていました。
ところが、実態は全然違っていて、相分離がなぜ起こるのかというメカニズムをはじめ、
- 相分離によって生じた液滴がどのような機能を有しているのか
- 液滴がどのような生命活動の維持に貢献しているのか
- 液滴があるからこそ細胞内の現象を違和感なく理解できるようになった
といったかなり発展的な内容となっており、ど肝を抜かれました。
個人的にかなり腑に落ちた「酵素反応」の例
個人的にかなりしっくりきた説明が「酵素」を用いた説明です。
酵素Xによって基質AからB、酵素ZによってBからCと、A→B→Cという連続反応があったとして、このときに酵素と距離わずかにでも離れると反応は進まなくなりますが、ところが細胞の中ではこの反応が起きています。
細胞の中で基質と酵素がランダムでぶつかり合ってこの反応が起こるのはよくよく考えたら効率がよくないですね。
ではどうやって反応が起こっているのか?という疑問に対して、形成された液滴内に高密度に酵素XとZが存在することで基質Aが液滴内で反応が始まると、途中で拡散せずに一連の反応が一箇所でまとめて起きるということが説明されていました。
なぜかこの部分がとても腑に落ちて印象的でした。
上記のような感じで、相分離によって液滴が生じるからこそ、細胞内の現象について納得のいく説明ができるようになってきたというのが確かに面白いと感じました。
物質を保護する機能
もう一つ印象的だったのが、液滴がタンパク質などを保護する機能についてです。
人間の体は常に一定な状態に保とうとする恒常性という機能がありますね。
これまでの私の認識は、変化に対して動じない安定性であったり、変化したものを元に戻そうというものでした。
相分離生物学では、変化しては困る(元に戻せないタンパク質など)ものを変化しないように保護する機能を持っていることも解説しており、必要な時に働く保護機能を搭載している細胞は本当にすごいなと感じました。
人間の体は変化に対して動じないことで一定に保っているという認識が、常に細かいところ(細胞内の数nmのスケール)で変化に対応していることで一定に保っているように見えているのだなという認識になりました。
相分離生物学を読んで面白かったところ
面白かった部分については説明されている現象というより、液-液相分離自体はかなり前から知られていたのに、なぜ細胞分野だと最近になってようやく注目されてきたのかという部分についてです。
このような単純な実験を、天然変性タンパク質が表沙汰にされてから10年以上もの間、なぜ誰もやってみようと思わなかったのだろうか?面白ものだが、天然変性タンパク質やプリオンの研究者に聞くと、誰もが同じように答える。2種類の天然変性タンパク質を混ぜると白濁し、光学顕微鏡で見ると数μmほどのドロップレットになってしまうが、このような状態にならないような実験条件を探して研究していたからなのである。白濁すると不均一な状態であると考えてしまい、NMRなどの分光学的な測定ができないと判断していたのである。
相分離生物学、白木 賢太郎、p44
では、なぜ特定の酵素がドロップレットを作るのだろうか?こういう疑問が生じるのは当然だ。しかし、この疑問に現在の私たちが答えることはできない。というのも、そもそもタンパク質が凝集すると凝集すると測定に支障がでるため、研究者は凝集しない条件を探して実験をしてきたからである。
相分離生物学、白木 賢太郎、p68
上記の引用部分のように、これまでタンパク質などの解析を行う時に、液滴ができた状態は不均一な状態で、溶解しておらず解析できないとのことで、綺麗に溶解した状態を作り出して解析をしてきたから気づくのが遅れたというのが非常に面白いですね。
もちろんこれは失敗でもなんでもなく、やっていることは悪いわけでもありません。むしろターゲットについて解析するために最善策を取っていたといっても過言ではないと思います。
こういう思い込みや先入観で見逃すことはその手のプロでも起きてしまうので、研究を行う上でとても大切なことだと感じました。
またこの結果、現在細胞内で生じる液滴についてはこれまで「起きない条件」を探してきたため、「起きる条件」についての知見は全然ないので、わかっている人が少ないというのも面白いですね。
オリジナリティを求めているのに、割と同じ方向に向かっていっているのだなと思うと、研究者の言うオリジナリティってなんなんだろうなと考えさせられました。
私たちは物事の原理を理解すればもっとうまくできる、いいものができると考えがちである。しかし、タンパク質のこのような研究から得られた結論はそれとは正反対である。要素が複雑にからまりあった現象は、タンパク質の立体構造という物理学的にはっきりした対象があったとしても、人間が理解できるような因果関係で解けるものではないのである。
相分離生物学、白木 賢太郎、p149
これは現在知られているタンパク質の構造・機能や過去の知見を元に、合理的にデザインすれば理想的なタンパク質を作ることができるのではないか?ということに対して、人間の頭で完結するほど単純な話ではないということを述べた文です。
少し勉強して詳しくなって、仮説を立てて挑んでも返り討ちにされたり、教授が自信満々に立てた実験計画を実行させられてもうまく行かないなんて経験をした人は多いと思います。
生命の現象は、数えきれないほどの変数が絡んだ超複雑な系であることを忘れずに驕らないようにというメッセージだと勝手に捉えて自戒することにします。
ちなみに本文では、タンパク質をデザインするときは、進化工学や物理法則の第一原理からコンピューターで計算する手法が主流になってきていて、その結果はなぜそうなったのか理解しにくいことが多いとのことで、人知を超えた科学になってきているとのことです。
今回取り上げた引用部分の文章から、思い込みや自分の考えが正しいという思考は大事なことを見落としたり、考えが行き詰まる原因になるのではないかと考えさせられました。
思い込みにとらわれず、常に自分の思考に問いかけをしながら研究に取り組まないと、人知を超えた科学に追いついていけないのかなと思います。
疑問が残っているところ
「相分離生物学」では液滴と表現されており、ゲルや凝集体と明確に区別されています。
これに対して、液滴が形成されるメカニズムを読んで、液滴内にある物質同士が何かしらの弱い結合する作用で近づきあっていることから、個人的にはかなり弱い結合(くっついたり離れたりがかなり起こりやすい)で架橋されたゲルのような印象が強かったです。
とはいえ、粘度やひずみや液滴の融合の様子について調べている結果を見ていると、やはり液滴なのかと思ったり、なんとも不思議な状態だなと一人考えふけっています。
本書では「液滴」「ゲル」「凝集体」の境界は、現在のところ研究者によって様々とのことで、まだまだ議論の途中なのだろうなと感じました。
こういった疑問を抱いた状態にしておくと、次からこの分野に触れる時に一つの大事な視点になると思うので、次から私が相分離生物学に触れるときはおそらく、液滴の持つ機能の他に、この物性の部分について注目していくのだろうと思います。
まとめ
以上、「相分離生物学」を読んで学んだことのアウトプットでした。
周りがとても盛り上がっていたので興味を持って読んでみた本でしたが、想像を絶するぐらい面白く引きずりこまれました。
確かにこれは盛り上がるわけですね。
まだまだ理解はできていないので、情報収集しながら勉強していきたいです。
生物の中で起きている現象を解明すること以外にも、とある条件下で液滴が形成されて、その液滴を形成する材料で液滴ごとに機能を持たせることができると言うのは、多少なりとも材料を扱っている身としてはかなり面白いと感じるところでありました。
人工的に目的の材料で目的の液滴を必要な時に形成させる制御ができるようになると、色々と面白いことができそうですね。(安直なところでいくとDDSとか真っ先に思い浮かびます)

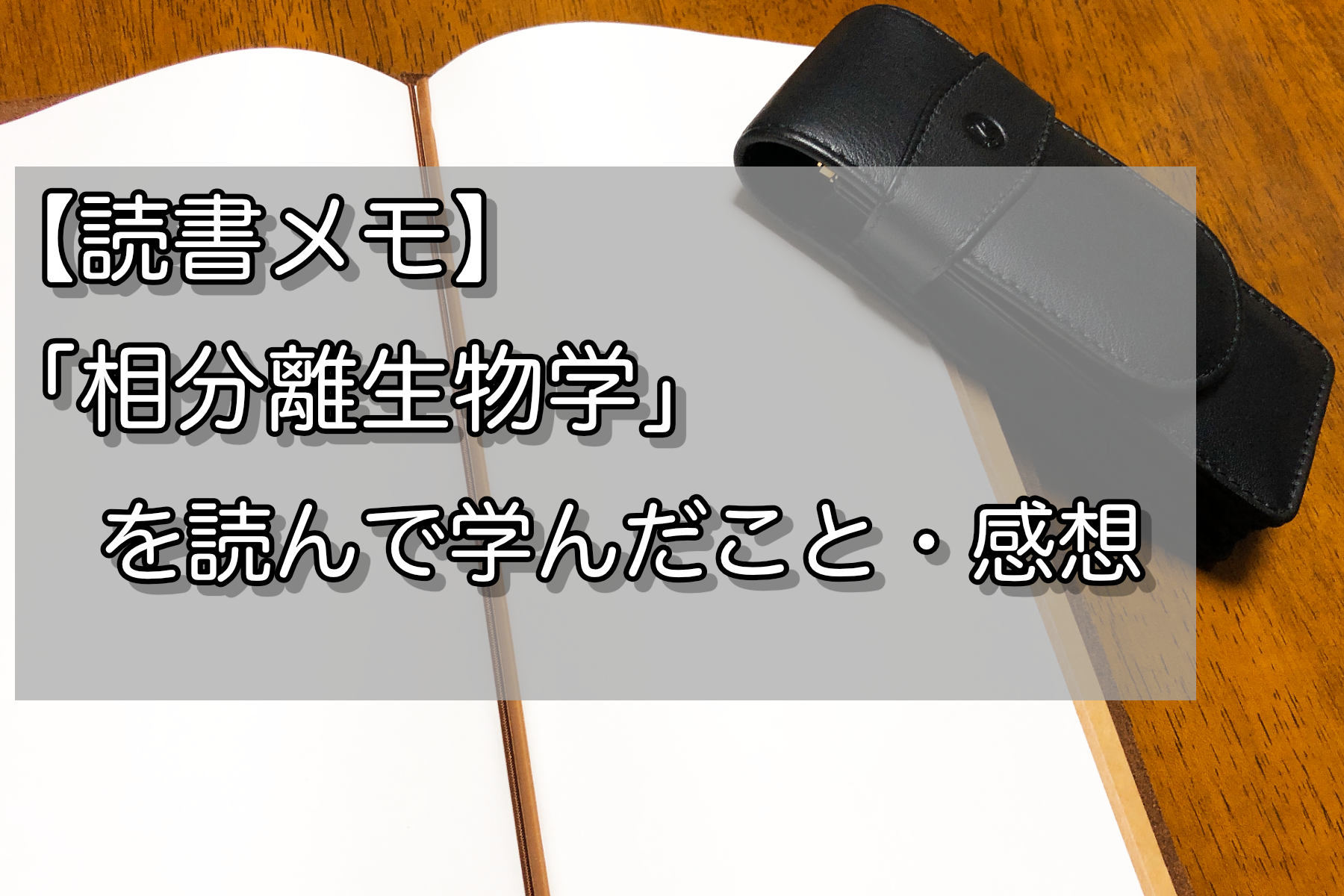


コメント